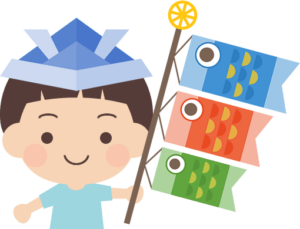保育園激戦区で「求職中」の私が入園を決めた方法【保育園選びのコツ】
保育園に通い始めたお子さんを持つママたち、またこれから保活を始める方々、来年度以降の保育園入園に不安を感じている方も多いのではないでしょうか?私の住む地域では、フルタイム復帰の育休明けの方々ですら多くが落選している現実があります。
そんな中、私は「求職中」の状態で無事に保育園の入園が決まり、子どもを預けることができました!
今回は、私がどのようにして保育園を決め、無事に入園を果たしたのか、その体験談をご紹介します。これから保活を始める方々に少しでも参考になれば嬉しいです。
まずは、私の状況を簡単にご紹介します。
- 夫はフルタイム正社員、育休なし
- 私は夫の転勤により復帰が困難となり、育休途中で退職(元々はフルタイム正社員)
- 地方で最も栄えている市に在住
- 求職中の条件で保育園に通いたい
- 4月の年度初めから保育園を希望
- 夫は勤務時間が遅いため、育児のメインは私
結論から言うと、私は1歳の子どもを認可外の小規模保育園に、企業連携枠を活用して4月から預けています。認可外保育園は高いというイメージがあるかもしれませんが、企業連携枠を利用することで、自治体や世帯収入によっては、認可保育園と同じくらいの金額で通うことができるんです!
それでは、私がどのようにして入園を決めたのか、順を追ってご説明します。
仕事を決めないと保育園が決まらない、でも保育園を決めないと仕事が決まらない!?
私が最初に直面したのは「仕事が決まらないから保育園が決まらない」「保育園が決まらないから仕事が決まらない」というジレンマでした。保育園に通わせることができれば仕事が決められると思い、役所に相談に行ったのは、子どもが生後6ヶ月の頃でした。
「保活は早く始めないと」と聞いていたので、早めに情報収集を始めたのですが、そこで驚くべき現実を知りました。私が住んでいる市では、認可保育園の入園は点数制。でも、待機児童が多く、求職中の私は点数が低すぎてほぼ不可能だと言われました。
そのため、一度仕事を探すことに決めました。しかし、ここで問題となったのは働き方です。私の希望は、土日祝休み、時短勤務、残業なしの仕事。求人サイトを毎日チェックし、面接にも進みましたが、子どもの預け先が決まっていないと内定が出ないと言われてしまいました。
本当に「仕事が決まらないから保育園が決まらない」「保育園が決まらないから仕事が決まらない」というジレンマにはまり、心身ともにストレスがたまる日々が続きました。
認可外保育園の選択肢—希望の光が見えた瞬間
仕事も保育園も決まらず悩んでいた私が次に目をつけたのは、認可外保育園でした。認可外は高いということはわかっていましたが、まず預け先を決め、その後仕事を決めるという戦略に切り替えることにしたのです。
認可外保育園は企業が運営しているところも多く、Instagramを活用して、来年度の園児募集情報を逃さないようにしました。さらに、電話で直接問い合わせ、申し込み時期や保育料を確認。ほとんどの認可外保育園は「4月から一気に子どもたちが入れ替わるので、早めに申し込めば入れますよ!」と回答してくれました。
また、認可保育園の結果が出た後にすぐに埋まってしまうこともわかり、認可外保育園を候補に加えることにしました。
認可外保育園で決断!—認可保育園からの切り替え
認可外保育園の情報を得て、私は認可外保育園に絞る決断をしました。そのため、保育園のInstagramで来年度の園児募集情報が出たらすぐに見学を申し込み、その日に枠を確保。複数の園を見学した結果、現在の園に申し込むことに決めました。
申し込みをしたその場で入園が決まり、見学を行ったのは2月。私はその月のうちに決まりましたが、認可保育園の結果が発表された際にはすぐに定員に達していたとのこと。認可外保育園に絞ったことで、無事に入園を決めることができました。
意外と安くなった!?保育料の秘密—企業連携枠を活用
認可外保育園に入園が決まったものの、気になるのは保育料ですよね。見学時には他の園と比べて安めの園に申し込んでいましたが、それでも「高いな…」と思っていました。
しかし、見学の際に先生から「企業連携枠」について教えてもらい、保育料を下げることができました!
「企業連携枠」とは、企業主導型保育園で、運営している企業の職員の子どもを優先的に預かる枠を譲ってもらう仕組みです。夫(またはどちらかの親)の勤務先と保育園が契約を交わすと、保育料が割引されます。
契約書に判子をもらうだけでOKなので、働いている会社に説明してOKをもらえれば、認可保育園と変わらない金額で預けられることもあります!
まとめ
保育園を決めることは大きな決断なので、焦らずに情報収集をして、選択肢を増やすと違った方向が見えてくるかもしれません!
私の体験が、これから保活を始める方々の参考になれば嬉しいです。自分と子どもに合った保育園を見つけて、より良い環境をつくれるといいですね。